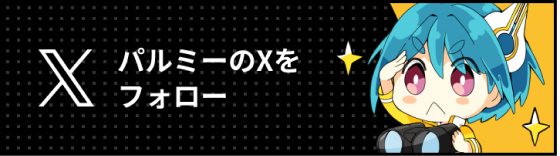アカデミックコース:美術解剖学講座
アカデミックコース:美術解剖学講座
パルミーには、美術の基礎をしっかり学びたい人向けの講座があります。
今回は、パルミー月謝制講座「アカデミックコース:美術解剖学講座」より、内容を一部抜粋してご紹介します。
人物の外形に影響する筋肉を学び、筋肉の始まりと終わりを知ることで人体の理解を深めていきましょう。
体のエリアごとの名称
人体の骨は、大きく 体幹・上肢・下肢の3つに分かれています。
骨の名前は全部覚えなくても大丈夫!大体の形やつながりを覚えていきましょう。
まず体幹は、体の中心部分の骨のこと。
頭蓋骨から始まって、胸郭、仙骨、背骨へとつながっています。

上肢は、鎖骨・肩甲骨・腕の骨がセットになっています。
腕を動かす時に動いている骨は、実は肩から先だけではなく鎖骨や肩甲骨も一緒に動いています。
実際に鎖骨を触りながら腕を回してみて確認してみましょう!

下肢は、骨盤からつま先までの骨のこと。
ふともも、すね、足の3つに分かれています。

また、上肢・下肢をさらに細分化していくと、鎖骨と肩甲骨を合わせて「上肢帯」、
骨盤と仙骨を合わせて「下肢帯」と呼びます。
全身がスラスラ描けるようになる!?
【初心者歓迎】超人気のジェスチャードローイング講座が公開中!わかりやすい動画授業+質問相談サポートで、あなたの上達を更に加速!【7日間の無料お試し実施中】
詳細はコチラ!男女の違い
男性と女性では骨格のつくりが違います。
この違いを意識すると、キャラクターの性別の特徴をはっきりさせやすくなります!
たとえば、男性は胸郭が大きくて骨盤が小さいので、ウエストのくびれは下の方になります。
一方で、 女性は胸郭が小さくて骨盤が大きいので、ウエストのくびれは上の方になります。

骨盤の形にも違いがあります。
男性の骨盤は穴が小さく、股関節の間隔が狭いのに対して、
女性の骨盤は胎児が通れるように穴が大きく、股関節の間隔も広いです。

さらに骨盤の角度も違っていて、
男性は骨盤がほぼまっすぐなのに対し女性は骨盤が傾いているので、
女性は腰の反りが強調されやすいという特徴があります。

イラストではこうした特徴を少し誇張して描くと、より男性らしさ・女性らしさが表現できます!
首周辺の筋肉
人間の体にはたくさんの筋肉・腱・靭帯があります。
今回は「外形(見た目)に影響する筋肉」に絞って解説していきます。

胸骨舌骨筋(きょうこつぜっこつきん)
この筋肉は胸骨(胸の中央の骨)から舌骨(ぜっこつ)に向かって伸びている筋肉です。

胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)
この筋肉は 胸骨と鎖骨の内側1/3あたりからスタートし、
耳の後ろにある骨の出っ張り乳様突起(にゅうようとっき)に向かって伸びています。

僧帽筋(そうぼうきん)
この筋肉は後頭部の出っ張りから背骨(第12胸椎)までの広い範囲から、
鎖骨の外側や肩甲骨の出っ張り肩峰(けんぽう)に向かって伸びています。
キリスト教のお坊さんがかぶる帽子に形が似ていることから僧帽筋という名前がつけられました。
首の動き方
首(頸椎)は、実は結構複雑に動く部分です。動きには大きく分けて3種類あります。
1つ目は 前後に動かす(屈曲・伸展) で、前に倒したり、後ろに反らしたりする動き。
2つ目は 横に傾ける(側屈) で、首を左右に傾ける動き。
3つ目は ひねる(回旋) で、首を回す動きです。
特に第一頸椎と第二頸椎が大事なポイントです。
第一頸椎は輪っかのような形をしていて、第二頸椎にはこの輪っかにはまる「軸」がついています。

この構造のおかげで、首を回すことができるんですね。
ただし、 頸だけで真横を向けるのは45度くらいが限界で、
真横を向くポーズの時は肩や背中の筋肉も連動して動いています。
美術解剖学の勉強法
この講座は講師の三澤寛志先生の著書をもとに解説しています。
美術解剖学の技法書を買ったのに、読まずに積んでいる…という人、いませんか?
そんな方にオススメの技法書を活用するためのポイントも紹介します!
絵だけ見て終わるのではなく、 文章もしっかり読むことが大事!
技法書の説明文には、描くときのヒントがたくさん詰まっています。
また、1冊読んだからといって、美術解剖学のすべてをマスターできるわけではありません。
本によって解説の仕方や視点が違うので、 いくつか読み比べて理解を深めていくのもオススメです。
いろんな視点から美術解剖学を学んだら、自分の描きたい表現に合わせて活かしていきましょう!
「アカデミックコース:美術解剖学講座」をもっと詳しく動画で解説!7日間の無料お試しで視聴しよう!
パルミーの月謝制講座「アカデミックコース:美術解剖学講座」では、人体の構造をより詳しく動画で解説しています。

時間割
- 全身の筋肉
- 講座概要・講師紹介
- 体のエリアごとの名称
- 首周辺の筋肉
- 上肢の筋肉
- 体幹の筋肉
- 下肢の筋肉
- 男女の違い
- 上肢の可動
- 首の動き方
- 腕の動き方
- ひじの動き方
- 前腕の動き方
- 手首の動き方
- 下肢の可動
- 背骨の動き方
- 脚の動き方
- 膝関節の動き方
- 足首の動き方
- まとめ:美術解剖学の学び方
動画では図解や模型を使って解説しており、効果的に人体の理解度を高められる講座です。
筋肉の形状を描けるようになりたい人は、ぜひ講座を受講してみてください。
無料お試しでは、この講座をはじめとする200以上の講座が全部視聴できます!
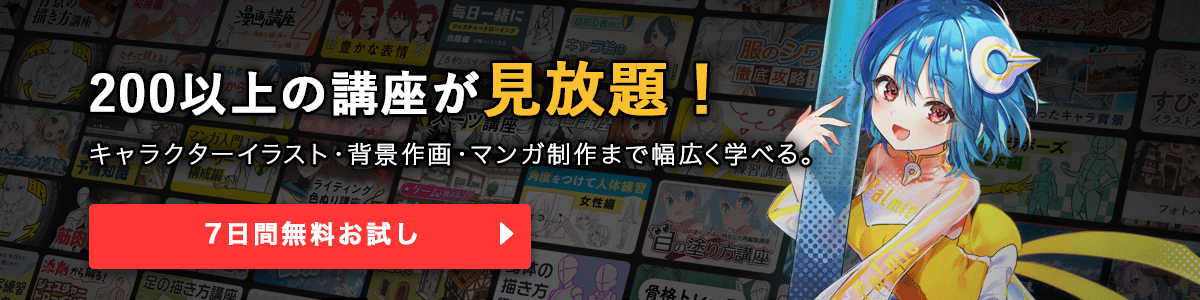
パルミーには、美術の基礎をしっかり学びたい人向けの講座があります。
今回は、パルミー月謝制講座「アカデミックコース:美術解剖学講座」より、内容を一部抜粋してご紹介します。
人物の外形に影響する筋肉を学び、筋肉の始まりと終わりを知ることで人体の理解を深めていきましょう。
体のエリアごとの名称
人体の骨は、大きく 体幹・上肢・下肢の3つに分かれています。
骨の名前は全部覚えなくても大丈夫!大体の形やつながりを覚えていきましょう。
まず体幹は、体の中心部分の骨のこと。
頭蓋骨から始まって、胸郭、仙骨、背骨へとつながっています。

上肢は、鎖骨・肩甲骨・腕の骨がセットになっています。
腕を動かす時に動いている骨は、実は肩から先だけではなく鎖骨や肩甲骨も一緒に動いています。
実際に鎖骨を触りながら腕を回してみて確認してみましょう!

下肢は、骨盤からつま先までの骨のこと。
ふともも、すね、足の3つに分かれています。

また、上肢・下肢をさらに細分化していくと、鎖骨と肩甲骨を合わせて「上肢帯」、
骨盤と仙骨を合わせて「下肢帯」と呼びます。
全身がスラスラ描けるようになる!?
【初心者歓迎】超人気のジェスチャードローイング講座が公開中!わかりやすい動画授業+質問相談サポートで、あなたの上達を更に加速!【7日間の無料お試し実施中】
詳細はコチラ!男女の違い
男性と女性では骨格のつくりが違います。
この違いを意識すると、キャラクターの性別の特徴をはっきりさせやすくなります!
たとえば、男性は胸郭が大きくて骨盤が小さいので、ウエストのくびれは下の方になります。
一方で、 女性は胸郭が小さくて骨盤が大きいので、ウエストのくびれは上の方になります。

骨盤の形にも違いがあります。
男性の骨盤は穴が小さく、股関節の間隔が狭いのに対して、
女性の骨盤は胎児が通れるように穴が大きく、股関節の間隔も広いです。

さらに骨盤の角度も違っていて、
男性は骨盤がほぼまっすぐなのに対し女性は骨盤が傾いているので、
女性は腰の反りが強調されやすいという特徴があります。

イラストではこうした特徴を少し誇張して描くと、より男性らしさ・女性らしさが表現できます!
首周辺の筋肉
人間の体にはたくさんの筋肉・腱・靭帯があります。
今回は「外形(見た目)に影響する筋肉」に絞って解説していきます。

胸骨舌骨筋(きょうこつぜっこつきん)
この筋肉は胸骨(胸の中央の骨)から舌骨(ぜっこつ)に向かって伸びている筋肉です。

胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)
この筋肉は 胸骨と鎖骨の内側1/3あたりからスタートし、
耳の後ろにある骨の出っ張り乳様突起(にゅうようとっき)に向かって伸びています。

僧帽筋(そうぼうきん)
この筋肉は後頭部の出っ張りから背骨(第12胸椎)までの広い範囲から、
鎖骨の外側や肩甲骨の出っ張り肩峰(けんぽう)に向かって伸びています。
キリスト教のお坊さんがかぶる帽子に形が似ていることから僧帽筋という名前がつけられました。
首の動き方
首(頸椎)は、実は結構複雑に動く部分です。動きには大きく分けて3種類あります。
1つ目は 前後に動かす(屈曲・伸展) で、前に倒したり、後ろに反らしたりする動き。
2つ目は 横に傾ける(側屈) で、首を左右に傾ける動き。
3つ目は ひねる(回旋) で、首を回す動きです。
特に第一頸椎と第二頸椎が大事なポイントです。
第一頸椎は輪っかのような形をしていて、第二頸椎にはこの輪っかにはまる「軸」がついています。

この構造のおかげで、首を回すことができるんですね。
ただし、 頸だけで真横を向けるのは45度くらいが限界で、
真横を向くポーズの時は肩や背中の筋肉も連動して動いています。
美術解剖学の勉強法
この講座は講師の三澤寛志先生の著書をもとに解説しています。
美術解剖学の技法書を買ったのに、読まずに積んでいる…という人、いませんか?
そんな方にオススメの技法書を活用するためのポイントも紹介します!
絵だけ見て終わるのではなく、 文章もしっかり読むことが大事!
技法書の説明文には、描くときのヒントがたくさん詰まっています。
また、1冊読んだからといって、美術解剖学のすべてをマスターできるわけではありません。
本によって解説の仕方や視点が違うので、 いくつか読み比べて理解を深めていくのもオススメです。
いろんな視点から美術解剖学を学んだら、自分の描きたい表現に合わせて活かしていきましょう!
「アカデミックコース:美術解剖学講座」をもっと詳しく動画で解説!7日間の無料お試しで視聴しよう!
パルミーの月謝制講座「アカデミックコース:美術解剖学講座」では、人体の構造をより詳しく動画で解説しています。

時間割
- 全身の筋肉
- 講座概要・講師紹介
- 体のエリアごとの名称
- 首周辺の筋肉
- 上肢の筋肉
- 体幹の筋肉
- 下肢の筋肉
- 男女の違い
- 上肢の可動
- 首の動き方
- 腕の動き方
- ひじの動き方
- 前腕の動き方
- 手首の動き方
- 下肢の可動
- 背骨の動き方
- 脚の動き方
- 膝関節の動き方
- 足首の動き方
- まとめ:美術解剖学の学び方
動画では図解や模型を使って解説しており、効果的に人体の理解度を高められる講座です。
筋肉の形状を描けるようになりたい人は、ぜひ講座を受講してみてください。
無料お試しでは、この講座をはじめとする200以上の講座が全部視聴できます!
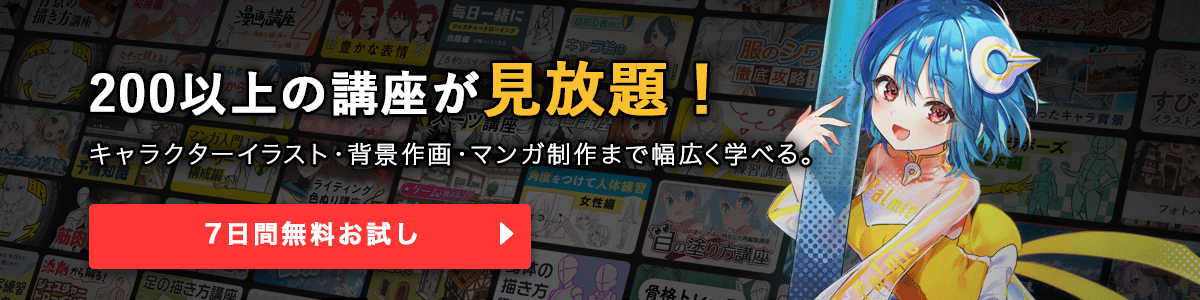
イラレポを投稿しよう